こんにちは、ジーピーオンライン(@gpol_tw)のぱらです。
Webサイト運用を担当されているみなさま、CMSについて業務を引き継ぐ新人スタッフに正しく説明できますか?
CMS(シーエムエス)とは「Contents Management System(コンテンツ・マネジメント・システム)」の頭文字を取った略称です。企業のサイト運用に携わっていらっしゃる方であれば、CMSを触ったことがある方が多いのではないでしょうか。
CMSは正しく理解することで、今後のWebサイト運用を大幅に効率化できる可能性を秘めています。
この記事では、Web担当者歴が浅い初心者の方に向けて、CMSの基礎知識から導入するメリット・デメリット、自社サイトに必要かの診断チェックポイントまでわかりやすく解説します。
新規導入から既存CMSの改修まで相談可能
CMSとは?

CMSとはWebサイトのコンテンツを更新するためのシステムです。
通常、Webサイトのページを作成・更新する場合、HTMLやCSSといったマークアップ言語の専門知識が必要です。しかし、CMSを利用すれば、言語の知識がなくても、掲載したい情報をブラウザ上で入力するだけでページを作成・更新が可能になります。
この手軽さから、企業のコーポレートサイトやオウンドメディア、ECサイトまで、規模や目的を問わず、非常に多くのWebサイトでCMSが活用されています。
従来のWeb制作との3つの根本的な違い
静的ページ、動的ページという言葉を聞いたことはありますか?動的ページと言われるものの大半がCMSで生成されているページとなります。Web制作の現場では、システムがはいっていない静的ページだけで作成されたサイトを静的サイトと呼びます。
次の3点はCMSがはいっているWebサイトと、従来のWebサイト(静的サイト)を比較した違いになります。
違い1:情報の管理方法(ファイル vs データベース)
まず、情報がどう蓄積されていくかという点で大きな違いがあります。
| CMSが導入されていないページ | CMSが導入されているページ |
|---|---|
| 各ページが独立したHTMLファイルとして存在。ページを増やす=ファイルを増やすこと。 | 文章や画像は「データベース」という箱に部品として保管。ユーザーがアクセスするたびに、テンプレートと組み合わせてページを生成します。 ページを増やす=データを増やすこと。 |
| 弊社サイトで例えると下記サービスページがCMSが導入されていないページです。 CMSが導入されていないページ事例のCMS構築サービスページ |
弊社サイトで例えるとこちらの制作実績ページがCMSが導入されているページです。 |
違い2:更新作業の場所(専門ツール vs 管理画面)
次に更新作業にフォーカスして違いをピックアップしました。
| CMSが導入されていないページ | CMSが導入されているページ |
|---|---|
|
|
違い3:サイトの性質(完成品 vs 成長する器)
最後はコンテンツの性質についてです。誰がコンテンツの制作責任者となるかが違います。
| CMSが導入されていないページ | CMSが導入されているページ |
|---|---|
| ページを追加・修正するたびに制作会社に依頼が必要。「完成品」を納品してもらうイメージ。納品物に関しては制作会社の責任範囲となります。 | 専門知識がなくても自社でページを追加・更新できる。「成長させるための器」を手に入れるイメージ。コンテンツに関しては自社で制作量産するため、責任は担当者が所属するチーム責任者になります。 |
CMSでできること
CMSの真価は、コンテンツ管理機能にあります。これにより、Webサイトは単なる情報掲示板から、価値ある情報資産へと変わります。
導入するCMSの種類や扱うコンテンツによって多少異なりますが、おおまかにCMSでできることは以下の通りです。
データファイルの管理
画像のアップロードや動画ファイルなど、ホームページに掲載したいファイルをCMS上で管理することができます。
ただし、CMSによってはアップロードの機能をカスタマイズする必要があったり、アップロードできるファイルの形式がCMSによって異なる違いがあるため注意が必要です。
ブログ機能
Webマガジンやブログ、コラムコンテンツなど自社からユーザーに向けて情報を発信するメディアのことを狭義の意味でオウンドメディアと言いますが、ブログ機能はこういったページを運営していく場合にほしい機能のひとつです。
文章、画像のレイアウトを自由に組めるものや、ある程度固定したレイアウトにするなどのカスタマイズが可能なCMSもあります。
テンプレート
ページの複製や、同一デザインのページを追加したい場合などに使える機能です。
汎用性のあるテンプレートを持たせておくことで、全体のデザインバランスを崩すことなくページの追加がおこなえます。
公開日時の設定
情報を更新したい日付をあらかじめ設定し、その日時になると自動的にアップされる機能です。
時間通りに情報公開しなければならない配信や、休業日に更新する必要がある場合に活用できます。
会員ページ管理
会員登録している人だけに特定の情報を発信したい場合に活用できる機能です。
ログイン情報を付与されたユーザーが、ブラウザ上でIDとパスワードを入力し、ログインして閲覧するページを表示する機能です。
データベースでの情報管理
例えばキャンペーンの応募者情報の管理や、自社製品の情報管理など、同じ項目の情報を多く扱う際に最適な機能です。
また情報を一斉にエクスポートしたい場合も、CSVファイルなどにダウンロードすることが可能です。
ユーザー権限・ロール管理
「管理者」「編集者」「投稿者」など、担当者ごとに操作できる範囲を設定可能。「新入社員はブログ投稿のみ、課長は全ページの承認権限を持つ」といった柔軟な運用が実現します。
ワークフロー・承認システム
記事公開までの「下書き → レビュー → 承認 → 公開」といった社内承認フローをシステム化。複数人での分業体制をスムーズにし、公開前のチェック漏れを防ぎます。
カテゴリー・タグ管理
コンテンツを「カテゴリー」で分類し、「タグ」で関連付ける機能。「お知らせ」「導入事例」といった分類や、「#新製品」「#セミナー」といった横断的なキーワードで情報を整理し、ユーザーが必要な情報を見つけやすくします。
CMSを導入するメリット・デメリット
CMSはWebサイト運用を劇的に変化させる力を持つ一方、導入前に理解しておくべきデメリットも存在します。
ここでは、CMSのメリットとデメリットをそれぞれ具体的に掘り下げて解説します。両者を正しく天秤にかけ、自社にとって本当に導入価値があるのかを判断する材料にしてください。
劇的変化!4つの導入メリット
CMS導入がもたらす変化は劇的です。主な導入メリットを4つ絞りました。
1.専門知識なしで簡単にページ作成・更新が可能
CMSを導入する最大のメリットは、HTMLやCSSといった専門知識(技術)がなくても、Web担当者が自社のタイミングで簡単にページを作成・更新できる点にあります。
多くのCMSでは、Microsoft WordやGoogleドキュメントのような見たまま編集できる画面(エディタ)が用意されており、テキストの入力や装飾、画像の挿入などを直感的に操作することが可能です。これまで制作会社に依頼していた軽微な修正や、急ぎのお知らせページの公開なども、すべて社内で完結させることができます。
2.ホームページの更新スピードが劇的向上
緊急のお知らせや新着情報を、外注せず自社の判断で即時に公開できる点だけでも、CMSを導入すべきポイントのひとつです。タイムリーな情報を発信できることで、ユーザーにいち早く情報を届けられます。
ビジネスの変化に合わせたスピーディーな情報発信が実現し、マーケティング活動における機会損失を防ぐ効果も期待できるでしょう。更新頻度の高いコンテンツほど効果が最大化するのがCMS導入の最大メリットです。
3.複数人での分業・同時編集で運用を効率化
Webサイトの規模が大きくなるほど、更新作業は一人で抱えきれなくなります。CMSには、複数人で安全かつ効率的にサイト運用ができる「ユーザー管理機能」が搭載することができます。この機能を使えば、担当者ごとにアカウントを発行し、「記事の作成だけできる編集者」「公開権限を持つ承認者」といったように、役割に応じた細かい権限設定が可能です。
これにより、担当外のページを誤って編集・削除してしまうといった人為的ミスを防ぎ、セキュリティを確保しながら分業体制を構築できます。
例えば、各部署の担当者がそれぞれのお知らせを直接更新したり、マーケティング部門と制作部門が連携してコンテンツを作成したりと、組織全体でWebサイトを活用していく上で、この機能は欠かせないものと言えるでしょう。
4.デザインの統一性を保ち、ブランドイメージを守れる
CMSを利用すると、Webサイト全体のデザインやレイアウトの統一性を簡単に維持できます。
CMSでは、あらかじめ「テンプレート」と呼ばれるサイトの雛形が用意されており、新しいページを作成する際は、テキストや画像を流し込むだけでページが完成します。HTMLでページを個別作成する場合、担当者のスキルによってデザインにばらつきが出てしまうことがありますが、CMSを使えば、誰が更新しても常に統一されたデザインのページを生成できます。
これにより、サイト全体のブランドイメージを損なうことなく、ユーザーにとっても見やすくわかりやすいサイト構造を保つことが可能です
CMS固有の3つのデメリットと対策
CMS導入には注意点もあります。事前に把握して対策について検討しておきましょう。
1.導入と運用にコストがかかる
CMS導入時にはシステム開発が必要になります。
開発作業はもちろんですが、ほかにも仕様書の作成やユーザーテストなどが必要になり、通常のホームページ制作より時間を要するほか、初期費用がかさむ傾向にあります。
初期費用は、CMSや必要機能によって費用は大きく異なります。WordPressのようなオープンソースCMSはソフトウェア自体のライセンス費用は無料ですが、サーバー代やドメイン代、そしてサイト構築を制作会社に依頼する場合はその開発費用(数十万~数百万円)が発生します。
一方、ベンダーが提供するパッケージCMSやクラウドCMSは、初期費用に加えて月額の利用料がかかるのが一般的です。また、導入後もシステムのアップデートやメンテナンス、セキュリティ対策といった保守作業が必要となり、これらを自社でおこなえない場合は、保守管理費用が別途発生します。無料のCMSであっても、長期的に見れば人件費や管理の手間といった「見えないコスト」がかかることを念頭に置いておくことが重要です。
2.定期的なセキュリティ対策が必須
CMSは便利な反面、ブラウザとインターネット環境さえあれば更新ができるため、不正アクセスなどのサイバー攻撃を受ける可能性があります。
インターネット上に公開されているCMS、特に世界中で圧倒的なシェアを誇るWordPressのようなオープンソースCMSは、常にサイバー攻撃の標的となるリスクを抱えています。CMSのプログラムに脆弱性(セキュリティ上の欠陥)が見つかると、それを狙った不正アクセスやサイトの改ざん、情報漏洩といった被害につながる可能性があります。
社内にセキュリティに詳しい専任者を配置したり、自社での対応が難しい場合は、保守サービスを提供している制作会社やベンダーに依頼することを検討しましょう。
【関連記事】企業のCMSセキュリティ対策6選!脆弱性とリスクについて解説
3.操作方法の学習が必要になる
「専門知識が不要」とはいえ、CMSを初めて利用する場合は、その管理画面の操作方法やコンテンツの作成ルールなどを覚えるための学習時間が必要です。
CMSによって管理画面のインターフェースや機能はさまざまで、高機能な製品ほど操作が複雑になる傾向があります。Webサイトの更新担当者が複数いる場合は、全員が基本的な操作を習得するための社内研修やマニュアル作成が必要になるかもしれません。
せっかくCMSを導入しても、担当者が使い方を理解できずに更新が滞ってしまっては意味がありません。そのため、CMSを選定する際には、いきなり多機能なものを求めるのではなく、自社の担当者のITスキルやリテラシーに合った、直感的で使いやすいシステムを選ぶことが重要です。無料のトライアル期間などを活用して、事前に操作性を確認することをおすすめします。
CMSの主な種類と特徴
CMSは、その提供形態によって大きく3つの種類に分類されます。それぞれの特徴を理解し、自社の目的や体制に合ったものを選ぶことが重要です。

オープンソース型CMS
オープンソース型とはソースコードが無償で公開されているCMSのことです。WordPressが代表的で、世界No.1のシェアを誇ります。無料である点と、豊富なプラグインによる高いカスタマイズ性がメリットです。一方、公式サポートはなく、セキュリティ対策は自己責任となります。
【関連記事】オープンソースCMSとは?企業サイト導入のメリット・リスクとおすすめ3選
SaaS型(クラウド型)CMS
クラウド型とは、サーバーごとサービスとして提供されるCMSサービスです。すでに用意されているCMSとなるので、導入スピードの速さはメリットですが、カスタマイズ要件が多いとメリット享受がなくなります。また、サーバー管理やアップデートが不要で手軽に始められますが、デザインや機能のカスタマイズ性は低い傾向にあります。
独自開発型(パッケージ型)CMS
パッケージ型は「買い取り型」とも言われていて、制作会社などが開発・販売する商用CMSです。手厚いベンダーサポートと高いセキュリティがメリットですが、ライセンス費用が高額になる傾向があります。企業のコーポレートサイトのような、大規模で高い信頼性が求められるケースに向いています。
独自開発型CMSとして、ジーピーオンラインのWOW(ワウ)があります。
【診断】あなたの会社にCMSは必要か?
CMSは非常に便利なツールですが、すべてのWebサイトに必須というわけではありません。数ページしかなく、今後も更新予定がほとんどないサイトであれば、導入コストや手間が見合わない可能性があります。
自社にとって本当にCMSが必要なのか、客観的に判断するための材料を提供します。以下の「導入に向いているホームページの特徴」と「CMSが必要?判断基準チェックリスト」を参考に、あなたの会社での必要性を診断してみてください。
導入に向いているホームページの特徴やコンテンツ3つ
CMS導入が特に効果を発揮するのは、以下のような特徴を持つホームページです。
更新頻度の高いNEWSやIRコンテンツ
ニュースリリースやIR、お知らせなどの配信をしている企業は多いのではないでしょうか。定期的、あるいは不定期だけど月に一定の回数発生する場合には、CMSの導入をおすすめします。
「急にリリースを配信しなくてはならなくなった」など緊急を要する場合も制作会社に依頼をせず、担当者で投稿できるためスピーディーな情報公開につながります。
複数人で発信するブログやコラムコンテンツ
複数人でHTMLファイルを更新する場合、誤って古いデータがアップされてしまったり、順番を待って1人ずつ編集する必要があったりと、リスクも手間も発生します。CMSを利用すると、コンテンツのカテゴリーごとに作業を分担することが可能です。
またCMSによってはアカウントごとに権限の割り振りができ、「トップページの編集はできない」などのコントロールも可能になるため、各部署やスタッフの担当範囲内で更新することができます。
定期的に情報の入れ替えが必要な製品コンテンツ
メーカーや製造業など多くの製品や商品を取り扱う企業にとっては、新製品のリリースに伴い都度ホームページの更新が必要になることがあります。デザインやレイアウトを変えず、情報や画像のみを変更したページを追加したい場合にはCMSが最適です。
CMSが必要?判断基準チェックリスト
あなたの会社にCMSが必要か、以下のチェックリストで判断してみましょう。3つ以上当てはまる場合は、導入を強くおすすめします。
- 専門知識がなくても、誰でも簡単に更新できる体制にしたい
- お知らせやブログ、導入事例などを月2回以上更新したい
- Webサイトの更新業務を複数人で分担したい
- サイト全体のデザインやレイアウトの統一感を保ちたい
- スタッフ紹介や事例コンテンツなど将来的にページ数を増やしていく計画がある
- 更新のたびに制作会社に依頼しており、時間とコストがかかっている
- 今後、コンテンツマーケティング(ブログ記事など)に力を入れたい
CMSに関するよくある質問
WordPressと他のCMSとの違いは何ですか?
WordPressは、世界で最も利用されているオープンソースのCMSです。元々はブログ作成ソフトとして開発されたため、記事の投稿や管理機能に優れています。最大の魅力は、圧倒的な情報量の多さと、豊富なテーマ(デザインテンプレート)やプラグイン(拡張機能)による高いカスタマイズ性です。ライセンス費用が無料な点も大きなメリットです。
一方、他のパッケージCMSやクラウドCMSは、特定の用途(例:BtoB企業のマーケティング、大規模なコーポレートサイト管理など)に特化した機能が充実していたり、ベンダーによる手厚いサポートが受けられたりする点が異なります。セキュリティ面でも、ベンダーが責任を持つ商用CMSの方が一般的に安全性が高いと言えます。
どちらが良いかは一概には言えず、コスト、カスタマイズ性、サポート、セキュリティなど、自社の方針や何を重視するかによって最適な選択は変わってきます。
【関連記事】WordPressの脆弱性への対策方法・チェック方法について
無料のCMSと有料のCMS、どちらが良いですか?
無料(オープンソース)のCMSと有料(パッケージ/クラウド)のCMSのどちらが良いかは、企業のWebサイト運用体制や目的によって異なります。
無料のWordPressは、コストを抑えたい、デザインや機能を自由にカスタマイズしたい、そして何よりシステム管理やセキュリティ対策を自己責任でおこなえる技術力やリソースがある企業に向いています。
一方、有料のCMSは、専門知識を持つ担当者が社内にいない、トラブル時に迅速なサポートを受けたい、高度なセキュリティを確保したい、といった企業におすすめです。有料CMSはコストがかかりますが、その分、運用にかかる手間やリスクを大幅に削減でき、担当者はコンテンツ作成という本来の業務に集中できるという大きなメリットがあります。自社の人的リソースや予算、そしてWebサイトに求める要件を総合的に判断して選ぶことが重要です。
【関連記事】企業サイトCMS比較!おすすめ8選と選び方のポイントも解説
導入にかかる期間はどのくらいですか?
CMSの導入にかかる期間は、Webサイトの規模や実装する機能、そしてどの種類のCMSを選ぶかによって大きく変動します。
例えば、既存のデザインテンプレートを使い、数ページ程度の小規模なサイトをクラウドCMSで構築する場合、最短で数週間程度で公開が可能です。一方で、オリジナルのデザインを作成し、基幹システムとの連携など複雑な要件を含む大規模サイトをパッケージCMSやオープンソースCMSで構築する場合は、要件定義から設計、開発、テストを経て公開に至るまで、半年から1年以上かかることも珍しくありません。制作会社に依頼する場合は、要件のすり合わせやコンテンツの準備状況によってもスケジュールは前後します。
導入を検討する際は、希望の公開日から逆算し、余裕を持ったスケジュールを立てることが成功のポイントです。
【関連記事】Webサイト制作の流れを分かりやすく解説!進め方のポイントと基本ステップ
まとめ:CMSは“更新の民主化”を実現する基盤
本記事では、CMSの基礎知識から、その仕組み、メリット・デメリット、そして失敗しない選び方のポイントまでを網羅的に解説しました。
CMSは、これまで専門知識を持つ一部の人に限られていたWebサイトの更新作業を、多くのWeb担当者の手に取り戻す“更新の民主化”を実現する基盤です。
導入効果は、スピード・コスト・品質・ガバナンス・SEOの多方面に波及。一方で、設計・セキュリティ・運用ルールは不可欠です。重要なのは、「オープンソース」「パッケージ」「クラウド」といったCMSの種類ごとの特徴を正しく理解し、自社のWebサイトの目的や規模、運用体制、そして予算に最も合ったシステムを見極めることです。
その上で、CMS導入は小さく始めて拡張し、継続的に改善することが成功の鍵と言えます。
ジーピーオンラインではWebサイトリニューアル時にいきなり大規模なCMS導入をおこなうのではなく、まずは小さく始めて事業の成長にあわせて改善・拡張していく、といった柔軟なCMS構築をご提案できます。CMS導入でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
新規導入から既存CMSの改修まで支援が可能
ジーピーオンラインのCMS構築サービス
CMS(Contents Management System)とは、専門の知識がなくてもWebサイトのコンテンツを自由に更新できるシステムのことです。オープンソース型と独自開発型の2つのタイプがあり、WordPressやDrupalはオープンソースの代表例です。一方で、独自開発型は商用パッケージ製品であり、ジーピーオンラインでは、独自開発CMSであるWOW(ワウ)を提供しています。
WOW導入事例
WOWは、2000年の創業時にVer1.0が開発され、25年に渡って多くのWebサイトへ導入されてきました。2023年にはVer3.0としてユーザーインターフェースの刷新およびユーザビリティ向上を実現しています。
- 自動車関連企業さまキャリア向け採用サイト
- 設備機器の卸売企業さまコーポレートサイト
- 食品製造業さまキャンペーンシステム
- 教育系出版企業さま電子書籍管理システム
- 金融系企業さまの記事型オウンドメディアサイト
ジーピーオンラインでは、お客さまが直面している課題に対して最適なCMS構築の提案をおこなっています。
CMSの選定からおまかせください!
会社案内・サービス資料を30秒でダウンロード
ジーピーオンラインの会社紹介・制作実績・プロジェクトの進め方を1冊に集約。Web制作パートナー比較検討に必要な情報をメールアドレスご入力後すぐにお届けします。
▼資料内容(一部)
-会社紹介
-事業紹介
-サービス紹介
-強みとこだわり
-多様な制作実績
-プロジェクトの進め方
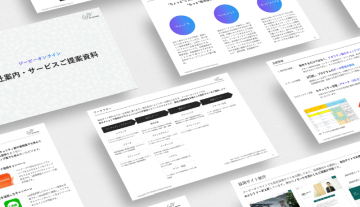
WRITERぱら 広報
コンテンツマーケティング会社でSNS運用を経験したのち、2018年にジーピーオンライン入社。Webサイト制作に関する情報をWeb担当者さま目線で分かりやすくお伝えします。


